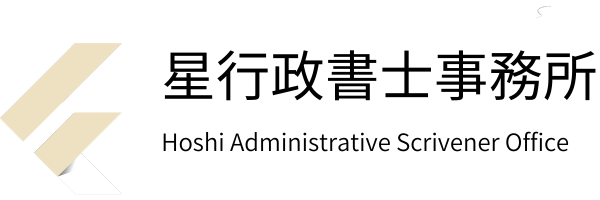遺言書作成ガイド ~大切な人に想いを届ける~
カテゴリー相続問題
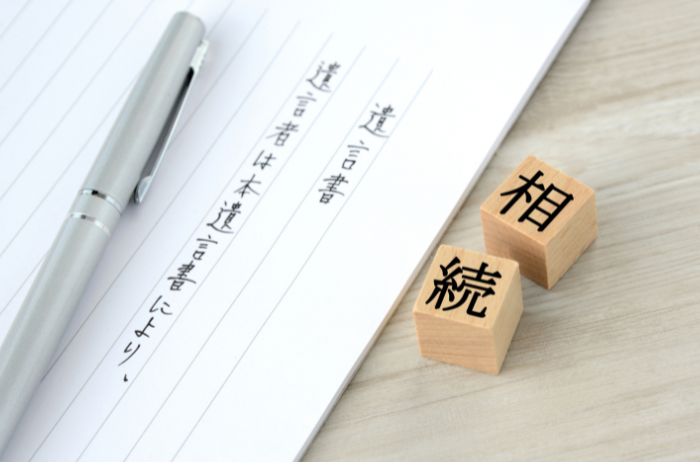
はじめに
「遺言書なんて、まだ早い」と思われる方も多いかもしれません。しかし、遺言書は年齢に関係なく、家族への気持ちを形にする重要な文書です。「もしもの時、家族が困らないようにしたい」「自分の想いをきちんと伝えたい」そんな気持ちをお持ちの方に、遺言書作成の基本知識をお伝えいたします。
遺言書が必要な理由

1.相続トラブルの予防
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。話し合いがまとまらないと、家族関係に亀裂が生じる可能性があります。
2.自分の意思の実現
- 特定の人に多く残したい
- お世話になった人に感謝を込めて
- 慈善団体に寄付したい
このような想いを確実に実現できます。
3.手続きの簡素化
遺言書があることで、相続手続きがよりスムーズに進みます。
遺言書の種類と特徴
1. 自筆証書遺言
自分で手書きする遺言書
メリット:
- 費用がかからない
- いつでも作成・変更可能
- 秘密が保たれる
デメリット:
- 法的要件を満たさないと無効
- 紛失・改ざんのリスク
- 家庭裁判所での検認が必要
注意点:
- 全文を自筆で書く(財産目録はパソコン可)
- 日付と氏名を自筆で記載
- 印鑑を押印(認印でも可)
2. 公正証書遺言
公証人が作成する遺言書
メリット:
- 遺言は無効になることがない
- 偽造・紛失の心配なし
- 検認手続きが不要
デメリット:
- 費用がかかる
- 証人2名が必要
- 公証役場での手続きが必要
3. 秘密証書遺言
内容を秘密にしつつ、存在を明確にする遺言書 ※実際にはあまり利用されません
遺言書作成の手順
Step 1: 財産の整理
すべての財産を洗い出しましょう
- 不動産(土地・建物)
- 預貯金・有価証券
- 保険金・退職金
- 借金・ローン
- 貴重品・骨董品など
Step 2: 相続人の確認
法定相続人を正確に把握しましょう
- 配偶者
- 子ども(養子含む)
- 両親
- 兄弟姉妹
Step 3: 分割方針の決定
誰に何を相続させるか決めましょう
- 配偶者の生活保障を優先
- 子どもたちの事情を考慮
- 遺留分への配慮も重要
Step 4: 遺言書の作成
選択した方式で作成します
遺言書作成時の注意点
1. 遺留分への配慮
法定相続人には遺留分(最低限の相続権)があります。遺留分を無視した遺言は、後にトラブルの原因となる可能性があります。
2. 明確で具体的な記載
- 財産の特定は正確に
- 「相続させる」と「遺贈する」の使い分け
- 曖昧な表現は避ける
3. 定期的な見直し
- 家族構成の変化
- 財産状況の変化
- 気持ちの変化 これらに応じて定期的に見直しを行いましょう。
4. 保管方法
自筆証書遺言の場合
- 法務局での保管制度を利用(別途費用がかかります)
- 信頼できる人に預ける
- 貸金庫での保管
遺言書以外の準備
1,エンディングノートの作成
遺言書では書ききれない想いや、葬儀の希望、大切な人へのメッセージなどを記載します。
2,生前整理
- 不要な物の整理
- デジタル遺品の1,
- 重要書類の整理
よくある間違い

❌ 夫婦で一通の遺言書を作成
共同遺言は無効です。必ず各自で作成してください。
❌ 鉛筆で書く
消えやすい筆記具は避け、ボールペンなどで書きましょう。
❌ 訂正方法を間違える
厳格な訂正方法があります。不安な場合は書き直しましょう。
まとめ

遺言書は、家族への最後のお手紙です。「まだ早い」と思わず、元気なうちに準備することをお勧めします。
遺言書作成のポイント:
- 財産と相続人の正確な把握
- 法的要件を満たした記載
- 遺留分への適切な配慮
- 定期的な見直し
複雑な財産がある場合や、家族関係が複雑な場合は、専門家にご相談いただくことで、より確実で安心できる遺言書を作成できます。
大切な家族のため、そして自分自身の安心のためにも、遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。